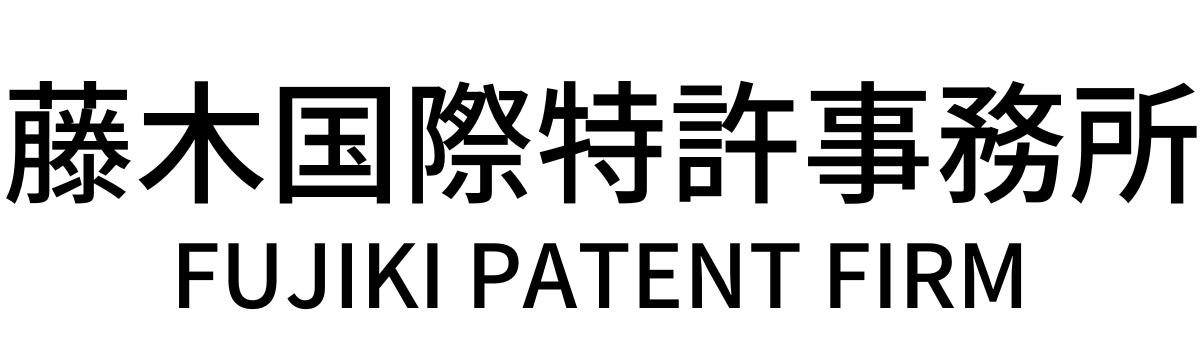米国で特許出願をする場合、米国でのFinal Office Actionに対する応答は、選択肢も比較的多く、検討内容も多いため企業担当者も、日本弁理士や現地代理人と相談することが多い手続きではないだろうか。Final Office Actionに対する応答については、Final Office Actionを受けるまでの経緯、審査官の見解、技術内容等を鑑みて、私も企業担当者とよく検討を行っていた。Final Office Actionに対する選択肢の概略とその選択肢の検討の思考過程が多少の参考になればと記事を作成した。但し、個別のケースに応じて検討事項は大きく変わるため、検討事項の選択肢を示す形式とした。また、こちらの記事ではあくまでも概略のみを記載しており、さらに詳細な内容までは記載していない。さらに、私は機械分野での米国出願が多いため、異なる分野では戦略が変わりうることは注意されたい。あくまでも個人的な意見のため、情報については自らご確認ください。
Final Office Actionが出される場合
米国でのFinal Office Actionは、原則的には2回目以降のOffice Actionであり、1回目のOffice Actionに対して、出願人の補正により次のOffice Actionを出す必要が生じる場合になされる(MPEP 706.07(a))。
Final Office Actionを受けにくくする方策については、米国でのOffice Actionを受けにくくする論点とも関連し、ご存じの通りこちらも奥が深い、こちらでは割愛するので個別にご相談ください。
補正(Amendment)
補正の内容が制限される点に注意が必要である。
新規事項(new matter)の追加はもちろん認められない。
補正が認められる場合(i)請求項のキャンセル、あるいは、オフィスアクションで指摘された形式に対応する補正、(ii)審判の為に拒絶された請求項をよりよい形式にする補正、(iii)内容的な補正であっても、補正が何故必要であり/かつ以前に提出できなかった有効で十分な理由がある場合の補正。
補正を認める(enter)するかどうかは審査官の裁量となる。
新しい争点(new issue)を提起する等のケースで補正が認められない場合には、後述するRCE(Request for Continued Examination)を行って補正することになる。
実際には、補正が認められるかグレーな場合も多く存在する。
グレーな場合にどうするか、Final Office Actionに対してAmendmentを出しても基本的にはenterされないが、まれにenterされるケースもあるので、明らかな新規事項(new matter)の追加のケースを除き、RCEを出す前に粘ってみる価値はある。
実際には、下記のAFCP2.0を使うか、現地代理人にtelephone interviewを行ってもらうか等と合わせて検討する。
担当審査官のこれまでの意見や審査内容も、今後の方針の判断材料として有効である。
担当審査官の審査傾向情報が手に入る場合があり、その場合には今後の戦略の参考にする。
さらには、行いたい補正の内容、現地代理人の費用感、等これらのさまざまな観点を総合考慮して対応を決定していく。
現地代理人の費用が高い場合には現地代理人にtelephone interviewを行ってもらう等の対応が取りにくい場合もある。
さらに、以下の観点も考慮する。
Final Office Actionに対して、6月以内にenterされなければ出願が放棄となる。よって、Final Office Actionに対して、RCEなしで補正書や意見書を提出する場合、AFCP2.0を使うような場合には、なるべく早い段階で提出する。Final Office Actionから2月以内に応答した場合には延長費用をAdvisory Actionの発送日から計算できる適用を受けられる場合もあるので、早めの応答が好ましい。このあたりはクライアントの対応方針やクライアント社内の処理プロセスのルールとも関係するため、早めに応答できる場合にはということになろう。
補正が認められるのが厳しそうな場合には、割り切って下記のRCE(Request for Continued Examination)をすぐに行うのも手である。インタビューのタイムチャージが高い現地代理人等の場合には費用を節約して、きっちり限定したクレームで審査を受けるのも一策である。
他方、後述するようにRCEの費用も比較的高いため、AFCP2.0を使いつつテレフォンインタビューをしてもらった方が効果が出る場合もある。
After Final Consideration Pilot 2.0(AFCP2.0)
最新の、米国特許商標庁(USPTO)のウェブサイトの情報によれば、After Final Consideration Pilot 2.0(AFCP2.0)は2023年の9月30日まで延長されるとのことである。
Final Office Actionに対する補正が審査官に見てもらえる可能性が高まるためAFCP2.0は検討する機会が多いはずである。請求料金も無料であるし、RCEを請求する前に、AFCP2.0のもとで補正書を提出できる。
補正をしない場合には、AFCP2.0は受けられない。
審査官は、3時間程度の時間で審査を完了し、拒絶理由が解消すれば、特許許可通知(Notice of Allowance)を出す。
教科書的には、拒絶理由が解消しない場合には、Interviewがなされるとあるが、Interviewが実施されずにAdvisory Actionが来るケースもある。言いたいことがあるのであれば、審査官の心証が決まる前に、先にtelephone interviewを申し込む方が効果的と思われる。
AFCP2.0は審査官のクレジットも付く上、短時間でも補正を見てもらえる可能性が高まるため、検討することが多い項目である。
Telephone interview
現地代理人にtelephone interviewを行ってもらう等も検討する。
審査官がそもそも発明の内容を誤解しているのではと思われるようなときには、現地代理人にtelephone interviewを行ってもらうことにより、誤解が解けて一気に許可に進むこともあるので、ケースによってはtelephone interviewも有効である。
AFCP2.0を使う場合には、telephone interviewを合わせて行ってもらうと効果的なケースも多い。
現地代理人にtelephone interviewを行ってもらう場合に注意すべき項目の一つは現地代理人の費用である。米国代理人の費用はそれなりに高いため、telephone interviewを行ってもらう場合には、ストーリーと骨子は原則日本代理人が準備する。日本側で準備をすることで現地代理人の費用を抑え、また意図する主張を確実に伝える。実力はあるが費用が高い現地代理人に検討を依頼する場合には費用のキャップを決めるという手もある。
Telephone interviewを行ってもらおうと思ったのにexaminerがすぐに捕まらないというケース、examinerが期間が短いと難色を示す等のケースも存在する。Final Office Actionに対してはtime period for replyもあるので、早めに対応が必要である。
Pre-Appeal Brief Request for Review
Pre-Appeal Brief Request for Reviewを行う際にはappealの請求も同時に行うことになる。
同時に補正は出せないが、事前に補正書を提出することはできる。しかしながら、補正は認められにくく、審査官の裁量である。
合議体による審査になるので、これまでの審査官の判断が非常に強引であると感じる場合には、Supervisorの目が入る点でメリットがある。
Pre-Appeal Brief Request for Review後に、審判理由書まで提出せずに、RCEで審査に戻ることも可能、その場合にはまともにAppealに入る場合の費用を抑えつつ、Pre-Appeal Brief Request for Reviewの手続きを受けることができる。
また、レビューの原案を日本サイドで作成すれば費用を抑えることが可能。
まともにAppealに入ればかなりの費用がかかるため、許容する環境があればよいが、突入する状況は限定される。
Pre-Appeal Brief Request for Reviewを選択するまでのプロセスには、RCEを繰り返して補正のネタが付きていたり、Pre-Appeal Brief Request for Reviewの活用についてはかなり局面が限られるが、継続審査となる場合があること、Pre-Appeal Brief Request for Review以後にRCEで審査に戻ることも可能である。Pre-Appeal Brief Request for Reviewには、他の副次的な効果もあると思われるが詳細は控える。
Request for Continued Examination (RCE)
RCE(Request for Continued Examination)は、Final Office Actionに対して審判請求をせずに審査を継続する手段として使用される。
RCEを検討するケースは多いと思われる。
Final Office Actionを受領した後、意見書補正書を提出する前にRCEを行うのか、Advisory actionを受けてからRCEを行うのかが実務的には検討することになろう。
RCEは、審査を継続できるという点で有効な手続きであると考えるが、USPTOの費用だけで、1回目$1,360、2回目$2,000の費用がかかる。従って、費用をいかに抑えていくかという検討も必要になる。
最後に雑感
元も子もないかもしれないが、最適解は存在していない。審査官が技術内容をしっかり見てくれない、現地代理人の費用が高い、発明者の確認が遅くなった、審査官とのInterviewの日程調整に時間がかかってしまった等、さまざまな状況も合わさって状況はさらに複雑化する。多様な選択肢の中から、何を重視して戦略を取っていくのかを考えねばならない。しかしながら、日本側のチーム(弁理士+企業担当者)で対応の選択肢もなるべく知っておくことで、企業にとって少しでも有効な選択肢が得られる可能性が上がると考えます。
弁理士・事務所紹介
 | 米国のオフィスアクションに対しては、現地代理人も重要ですが、日本の代理人も重要です。なぜなら、米国の現地代理人のチャージは非常に高額であり、現地代理人に対応方針の提案を任せると費用が高額となることが多くなるからです。一方で、クライアントだけで米国の対応を検討するのも一定の慣れたクライアントを除いてはなかなか難しいことが多いと思われます。そこで日本の代理人が米国の中間処理に関しても重要な役割を果たします。それこそ、米国のオフィスアクションに対してどうするかという最初のところから相談できることが大事と思います。一人で悩むよりお気軽にご相談ください。また、日本語が話せる現地代理人にこだわらない(もちろん素晴らしい方は沢山いらっしゃいますので場合によりますが)ことも一策です。112条の対応やInterview等現地人の感覚が生きやすい局面もありますし、気軽にInterviewをしてくれる現地代理人等の選択肢が広がります。日本の代理人がしっかり対応すれば戦略面もサポートがなされます。米国での権利化にはさまざまな問題が生じ、非常に多くの要素が絡み合うため悩みは尽きないところですが、相談できる水先案内人のような日本の代理人がいることで選択肢が広がるものと信じています。 |
経歴
1999年 私立巣鴨高等学校卒業
1999年 慶應義塾大学理工学部システムデザイン 工学科入学
2003年 慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科卒業
2003年 東京工業大学原子核工学専攻修士課程入学
2005年 東京工業大学原子核工学専攻修士課程卒業
2005年 弁理士試験合格
2008年 弁理士登録
2008年 中村合同特許法律事務所入所
2016年 会計系コンサルティング会社勤務
2017年 中村合同特許法律事務所入所
2019年 米国Birch, Stewart, Kolasch & Birch事務所研修プログラム修了
2019年 米国BakerHostetler法律事務所にて研修
2022年 藤木国際特許事務所開設
所属
2008年~ 日本弁理士会会員 登録番号15984号
2010年~2013年 日本弁理士会 知的財産支援センター専門委員
2022年~ 弁理士会派 春秋会 広報委員会専門委員
2022年~ 神奈川県中小企業家同友会所属
2022年~ 鎌倉商工会議所会員
2022年~ 鎌倉商工会議所青年部会員
2022年~ 一般社団法人首都圏産業活性化協会正会員
2022年~ 特許庁知財アクセラレーションプログラム IPAS2022ナレッジシェアプログラム参加
2022年~ 多摩イノベーションシステム促進事業コミュニティ参加企業認定
2022年~ スポーツビジネスネットワーク埼玉登録
2022年 特許庁知財アクセラレーションプログラム IPAS2022スタートアップ支援事業 アソシエイトメンター
2022年 特許庁知財アクセラレーションプログラム IPAS2022スポットメンタリング メンター
2023年 弁理士春秋会 幹事
2023年 日本弁理士会 特許委員会 委員